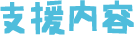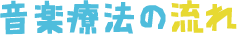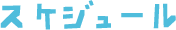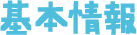児童発達支援「はなまる」は音楽に特化した
児童発達支援サービスの事業所です。

私たち「はなまる」スタッフは発達に不安のあるお子さま一人ひとりに寄り添い、一緒に音楽を楽しみながら成長を喜び合える場所になれることを願っています。



1.社会性が身につく
音楽療法士と一緒に音楽遊びを楽しむことで、家族以外の人との関わり方を学びます。学校や地域で必要なソーシャルスキルの獲得を促します。
2.コミュニケーション力が身につく
歌や楽器演奏は一人で行うものではなく、必ず音楽療法士と一緒に息を合わせて楽しく行います。合図に気づく、あいさつやお返事をする練習を活動の中で取り入れます。
3.運動能力が身につく
ワクワクするリズムに合わせて身体を動かす運動プログラムを取り入れることで、肌感覚で身体のバランスのとり方や、身体の使い方を身につけることを目指します。
4.豊かな表現力が身につく
ダンスや楽器活動を通して、お子さま自らが表現する活動を多く取り入れます。伝えたい気持ちを上手に楽器で表現できるようになることで、ストレスの発散にもつながります。表現することが「楽しい!」と感じられることを目指します。
5.自信をもって「できる!」を増やす
音楽療法ではお子さまが「自分でできた!」と感じられる成功体験をくり返し提供することで、自己肯定感を高めお子さまが自信を持って生活できるようサポートします。
6.リズム感・音感が身につく
音楽活動の中で自然と身につくのが音楽的な能力です。音楽教室に通うのが困難なお子さまも音楽療法士が丁寧に関わりサポートします。
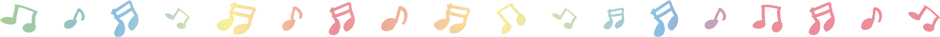
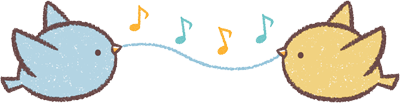
アセスメント
お子さまの日頃の様子や好みの音楽や番組をヒアリングします。実際に部屋に入り音楽療法士と一緒に楽器選びや音楽遊びを行います。アセスメントは初回に行います。
↓
目標設定
アセスメントで得た情報から、一人ひとりにあった長期目標と短期目標を設定し、お子さまにとって必要な支援を明確化します。
↓
プログラム設定
お子さまの年齢、生活状況、好みの音楽や絵本などの情報から、楽しみながら活動できるプログラムを設定します。
↓
音楽療法セッションの実施
一人ひとり異なるオリジナルのプログラムを進めます。その日の体調に合わせてプログラムを柔軟に変化させます。
↓
保護者へのフィードバック
音楽療法でのお子さまの様子や反応、上手にできたことや今後への取り組み、課題を保護者様へ直接口頭でフィードバックさせていただきます。
↓
記録
終了後には担当者がお子さまの様子や気づき、次回への取り組みを記録し、次回の音楽療法に役立たせます。
↓
振り返り
担当音楽療法士とスタッフチームが、今後の目標やプログラムの見直しを行います。保護者様への説明を行います。
| 1セッション | 40分 |
|---|---|
| 保護者へのフィードバック | 10分 |
- 10:00-10:50
- 11:00-11:50
- 13:00-13:50
- 14:00-14:50
- 15:00-15:50
- 16:00-16:50
支援プログラム (令和6年10月23日掲載)
児童発達支援事業所 はなまる
| 事業所名 | 児童発達支援事業所 はなまる | 支援プログラム | |||||||||||||||||||
| 法人(事業所)理念 | 「障害のある仲間たちとともに、誰もが安心して暮らせる社会を実現」 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援方針 | 生活能力の向上に必要なスキルの獲得や、社会との交流が適切に図れるよう支援していく。 地域及び家庭との結び付きを重視し、関係機関との連携に努めていく。 |
|||||||||||||||||||
| 営業時間 | 9 | 時 | 0 | 分から | 18 | 時 | 0 | 分まで | 送迎実施の有無 |
あり |
なし | |||||||||
| 支 援 内 容 | ||||||||||||||||||||
| 本人支援 | 健康・生活 | 楽器等の片付けや、身支度など、自立に向けて自分でできる事を増やせるように支援していく。
声掛けを行い水分補給やトイレを促していく。 気持ちよく過ごせる環境作りを行い情緒の安定を図る。 |
||||||||||||||||||
| 運動・感覚 | 好きな音楽を使った身体活動を取り入れ、楽しみながら粗大運動に参加できるよう支援する。 楽器や歌の活動を通して、力の調整や声の加減を練習できる環境を設定する。 |
|||||||||||||||||||
| 認知・行動 | 列に並んだり、周りを見て一緒に行動できるよう必要に応じて声掛けをする。 音楽活動の中で聴覚を活用して環境に気付き行動に移せるように支援していく。 |
|||||||||||||||||||
| 言語 コミュニケーション |
発声を伴う活動を通して、楽しみながら正しい発音を意識できるように支援してく。 単語を適切な環境で使う練習ができるよう支援する。気持ちをくみ取りながら共感の姿勢で寄り添い、受容される体験を提供する。 歌やリズム活動を通して楽しみながら発音の練習をして発達を促す。 |
|||||||||||||||||||
| 人間関係 社会性 |
音楽活動の中で、話す人を見る、聞く練習及び順番や交代を含む共同遊びの中でお友達と効果的なやりとりができるよう支援する。 距離が近い場面は声掛けや誘導により本人が気付き、適切な距離を保ち活動に取り組むことができるよう支援していく。 |
|||||||||||||||||||
| 家族支援 | ご本人に対しての対しての困りごとや、支援に関することの相談・助言を行う。 | 移行支援 | 園などの他機関との連携を必要に応じて対応をしていく。 | |||||||||||||||||
| 地域支援・地域連携 | 必要に応じて、関係機関で役割分担をしながら、情報を共有し、生活や支援に関する提案をしていく。 | 職員の質の向上 | 月1回の事業所内研修を実施。 外部研修への参加、伝達研修を実施。 |
|||||||||||||||||
| 主な行事等 | コンサートの開催、音楽交流会 | |||||||||||||||||||
株式会社きずな
児童発達支援事業所 きずな
| 名称 | 児童発達支援事業所 きずな |
|---|---|
| 事業所番号 | 345200782 |
| 所在地 | 〒739-0025 広島県東広島市西条中央6丁目6-8プレシアス中央302 |
| TEL | 082-437-3260 |
| FAX | 082-437-3261 |
支援プログラム (令和7年3月25日掲載)
児童発達支援事業所 きずな
| 事業所名 | 児童発達支援事業所 きずな | 支援プログラム | |||||||||||||||||||
| 法人(事業所)理念 | 「障害のある仲間たちとともに、誰もが安心して暮らせる社会を実現」 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援方針 | 応用行動学分析(ABA)を基に、問題行動の軽減と代替行動の習得、言語・社交性スキルの向上、自立身辺スキルの獲得を目指します。お子さまの発達段階に応じた支援を行い、家庭や地域と連携しながら、安心して成長できる環境を提供します。 | |||||||||||||||||||
| 営業時間 | 9 | 時 | 0 | 分から | 18 | 時 | 0 | 分まで | 送迎実施の有無 | あり | なし |
|||||||||
| 支 援 内 容 | ||||||||||||||||||||
| 本人支援 | 健康・生活 | "トイレ・食事・着替えなどの自立スキルを、ほめながら少しづつ習得できるよう支援する。 絵カードやスケジュール表を使い、1日の流れを分かりやすくし、お子さまの不安を減らす。 手順を細かく分けて練習し、一つひとつの成功体験を積み重ねながら習慣化する。 | ||||||||||||||||||
| 運動・感覚 | "遊びの中でジャンプやボール投げなどの動きを楽しく練習し、体の使い方を学ぶ。 簡単な動作から成功体験を増やしながら、少しずつ新しい動きを覚えられるよう支援する。 音や光に敏感なお子さまには、刺激を調節しながら安心できる環境を整えます。 | |||||||||||||||||||
| 認知・行動 | "機能分析に基づき、問題行動の要因を特定し、適切な代替行動を指導する。 プロンプトフェーディング(段階的な手助けの減少)を活用し、自発的な問題解決のスキルを育成する。 選択肢を増やし、自分で決める力を伸ばす。 | |||||||||||||||||||
| 言語 コミュニケーション |
"言葉が出にくいお子さまには、絵カードやジェスチャーを使ったコミュニケーションをサポートする。 「ちょうだい」「みせて」などのやり取りを遊びの中で練習し、会話のきっかけを作る。 会話の流れを学ぶために、繰り返しの練習やストーリーを活用する。 | |||||||||||||||||||
| 人間関係 社会性 |
"順番を待つ、ルールを守るなど、集団の中で必要なスキルを遊びながら学ぶ。 「ありがとう」「ごめんね」など、気持ちを表現する練習を行う。他者とのやり取りをサポートし、楽しく関われる機会を増やす。 | |||||||||||||||||||
| 家族支援 | "保護者向けの相談、ペアトレ、勉強会の実施。 家庭で使えるプログラムや、視覚的支援の提供。 きょうだい支援。 | 移行支援 | "保育園・幼稚園へ訪問、園と連携し適応スキルの練習。 集団生活に必要なスキルの指導。 先生向けに対処方法のアドバイスを提供。 | |||||||||||||||||
| 地域支援・地域連携 | 必要に応じて関係機関と情報を交換、共有し、生活や支援に関する提案をしていく。 | 職員の質の向上 | "月1回の事業所内研修を実施。 外部研修への参加、伝達研修を実施。 | |||||||||||||||||
| 主な行事等 | お花見・納涼会・お月見・ハロウィン・クリスマス会など季節ごとの行事、消防・避難訓練。 | |||||||||||||||||||